「鉄は火に弱い」──だからこそ“火の衣”で守る。
火災の熱は、どれほど強靭な鉄骨でもわずか10分ほどでフニャっと軟化させてしまいます。
倒壊が始まれば、人の避難も消防の初期消火も間に合いません。そこで登場するのが 耐火被覆。
自らは燃えず、かつ鉄骨を熱から遠ざける“外套(コート)”で、皆さんが設計・施工する建物の最後の砦です。
本記事では「そもそも耐火被覆って何?」という超基礎から、施行令107条・告示1399号のツボ、材料・工法の選定、そして現場で毎回モメる“グレーゾーン”の解きほぐし方までを一気通貫で解説。
さらにロボット吹付けなど最新DX動向も盛り込みました。
若手エンジニアが「明日から現場で使える」具体策をぎゅっと凝縮しています。
ぜひ最後まで読んで、火に負けない建築を一緒にアップデートしていきましょう!
耐火被覆って何者?
火災時に鉄骨がヘロヘロに溶けるのをガードする“外套(コート)”。
温度上昇を遅らせて避難時間を確保し、倒壊を防止するのがミッションです。
そのためには、自分が燃えない<耐火性>と、守るものの温度を上げない<断熱性>が重要です。
鉄骨は、高温に弱く、火災にあうと強度が著しく低下します。
建物内にいる人が安全に避難する時間を確保することが、耐火被覆が担う最も重要な役割なのです。
法規をギュッと整理
| 押さえ所 | キーワード | 一言メモ |
|---|---|---|
| 施行令107条 | 「○時間」耐火性能 | 柱・梁は1~3 h、屋根30 min |
| 告示1399号 | 構造方法&必要厚さ | ロックウール35 mm/H形鋼2 hなど |
| 木造合理化改正(2024) | CLT等は被覆緩和 | 大臣認定の活用がカギ |
施行令107条は、建築物の各部分が通常の火災による熱に対してどの程度耐えられるかを規定しています。
具体的には、建築物の壁、柱、床、屋根などが一定時間火災の熱に耐え、構造的な損傷(変形、溶融、破壊など)を生じないことが求められています 。例えば、耐力壁は1時間から3時間、屋根は30分間の耐火性能が必要とされています。この基準により、火災時に建物の安全性を確保し、避難や消火活動を支援することが目的です。
告示1399号は、建物の壁や柱などが火災時にどのように耐火性能を持つべきかを詳細に規定しています 。
例えば、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の厚さや、防火被覆の取り合い部分の構造方法などが具体的に示されています。これにより、建物の安全性を高め、火災時の被害を最小限に抑えることが目的です。
24年の木造合理化改正は、木造建築物の設計や建築に関する規制を緩和し、より効率的かつ安全に木材を利用できるようにすることを目的としています。
主な改正点は以下の通りです 。
- 構造計算の合理化:特定の条件を満たす木造建築物について、構造計算の簡略化が認められます。これにより、設計や建築の手続きがスムーズになります。
- 壁量計算の見直し:必要な壁量や柱の小径に関する基準が改正され、より実際の建築条件に即した計算方法が導入されます。
- 高さ制限の緩和:木造建築物の高さ制限が緩和され、より高層の木造建築が可能になります。
- 防火規制の合理化:防火区画の設置方法が見直され、木造建築物の設計の自由度が高まります。

鋼構造耐火設計指針
材料・工法オールスター図鑑
| 種類 | ここが強み | ここが弱み | 代表シーン |
|---|---|---|---|
| 吹付けロックウール | 安い・自由形状 | 粉塵・意匠△ | 多数 |
| 巻付け耐火被覆材 | 安い・早い | 意匠△ | 物流施設 |
| 防火被覆板(ケイカル板) | 早い・汚れない | 重い・曲面× | 柱・間仕切壁 |
| 膨張型耐火塗料 | 薄膜・美観◎ | コスト▲ | エントランス梁 |
| 耐火シート | リニューアル向き | 曲面△ | 設備更新 |
| セラミック系 | 屋外OK | 材料費▲ | 冷凍倉庫 |
スプレエース・マキベエ…聞き覚えのある銘柄は押さえておきましょう。

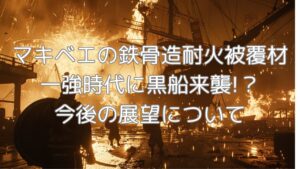
「この建物、被覆いる?」― 適用範囲の早見表
- 防火地域:延べ 100 ㎡超または3 階以上 → 原則フル被覆
- 準防火地域:延べ 1,500 ㎡超または4 階以上 → 準耐火
- 特殊建築物(劇場・病院など)は用途×規模で判定。建築基準法27条を要チェック。
- 水平力だけの筋かいは被覆不要だが、鉛直力も負担するなら必要。
| № | 用途グループ(※法別表1〈い〉欄) | 「耐火建築物」にしなければならない規模要件 | 備考・緩和ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | ① 3 階以上 ② 客席200 ㎡超(屋外観覧席は1 000 ㎡超) ③ 主階が1階にない場合 | いずれか該当で耐火建築物。ex)客席 200 ㎡以下でも3 階建てなら被覆要。 |
| 2 | 病院・診療所(入院施設あり)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等 | ① 3 階以上 | 3 階建てでも延べ200 ㎡未満は近年の改正で緩和(警報設備要)。それ以上は柱梁に被覆必須。 |
| 3 | 学校・体育館・博物館・美術館・図書館・ボウリング場・スケート/スキー/水泳場などスポーツ施設 | ① 3 階以上 | 緩和条文はなく、3 階建てになった時点で全面耐火→被覆が必要。 |
| 4 | 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物販店舗(※一部10 ㎡超で特建扱い) | ① 3 階以上 | 同グループは人が密集+可燃物多め=火災リスク大。面積条件はなく 3 階到達で被覆必須。 |
| 5 | 倉庫 | ① 3 階部分の床面積200 ㎡超 | 2 階建て以下は27条対象外。ただし倉庫は準耐火緩和がほぼ効かないので要注意。 |
| 6 | 自動車車庫・自動車修理工場・映画/TVスタジオ 等 | ① 3 階以上 | 3 階建てになった瞬間に耐火建築物。消防法との二重規制も忘れず。 |
チェックのコツ
- 「3 階以上」が最大トリガー。ほとんどの用途は階数でアウト。
- 2 階建てでも客席・床面積など個別面積条件に触れると被覆必須。
- 改正で生まれた延べ200 ㎡未満緩和(就寝系用途のみ)を活かせば、小規模リノベが楽に。
厚さ=性能チャートで失敗ゼロ
- H形鋼柱 2 h耐火:吹付け35 mm/けい酸Ca板20 mm以上
- 梁:4 階以下→1 h、5~14 階→2 h、15 階以上→3 h
→ 階数が上がるほど厚くなるのが鉄則。薄膜塗料なら認定FP番号で確認必須。
| 部材 | 要求耐火時間 | 吹付ロックウール※1 | けい酸カルシウム板※2 | 膨張型耐火塗料(SKタイカコート等)※3 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄骨柱 (H形鋼 500 ㎜以下) | 1 h | 25 mm | 15 mm | 2.0 mm (±0.2) |
| 2 h | 35 mm | 20 mm | 3.5 mm | |
| 3 h | 45 mm | 25 mm | 4.5 mm | |
| 鉄骨梁 (ウェブ高さ ≦600 ㎜) | 1 h | 20 mm | 12 mm | 1.5 mm |
| 2 h | 30 mm | 18 mm | 3.0 mm | |
| 3 h | 40 mm | 22 mm | 4.0 mm | |
| 床スラブ下梁 (デッキプレート併用) | 1 h | 18 mm | 12 mm | 1.2 mm |
| 鉄骨耐力壁・ブレース | 1 h | 25 mm | 15 mm | 2.0 mm |
| RC床・壁 (参考) | 2 h | ― | コンクリート t=100 mm | ― |
| 屋根トラス下弦 | 30 min | 15 mm | 9 mm | 1.0 mm |
※1 告示1399号例示仕様:かさ比重 200 kg/m³ 以上のロックウール吹付け。例:柱2 h → 35 mm
※2 ゾノトライト系けい酸カルシウム板(JIS A 5430)。柱2 h → 20 mm が標準
※3 発泡型耐火塗料「SKタイカコート」カタログ値。1 h=0.5-2 mm、2 h=~4.5 mm
使い方のヒント
- 部材断面が大きい場合は告示厚さを+5 mm 程度見込むと現場管理が楽。
- 発泡塗料は屋外・湿潤環境不可の認定が多いので FP 番号を要確認。
- 告示外ディテール(貫通部・補剛材等)は大臣認定 FP 編番号で厚さが変わる。
⚠️ 上表は代表値です。必ず最新の告示・FP認定書に照らし合わせ、部材寸法・使用環境に応じて設計してください。
実務のグレーゾーンと打ち手
1. 吹付け厚さの許容差 ― 「何ミリまで OK?」問題
告示1399号は最小厚さしか示しておらず、施工誤差の許容幅は一切言及されていません。
このため現場では「設計 30 mmに対して 27 mmで合格か否か?」という判定で揉めがちです。
- 背景
- 吹付けは職人の感覚と設備条件に左右され、±5 mm程度のムラは避けられない。
- 法的根拠がないため、監督・元請・検査機関それぞれで基準がバラバラ。
- 推奨アクション
- 設計図書に「厚さ管理基準 ±○○ %」を明記し、確認審査の早期段階で合意形成。
- レーザースキャナや点群計測を使い、全数厚さヒートマップで客観データを提示。
2. 屋根梁の耐火被覆免除 ― 「4 mか 3.9 mか」論争
施行令107条には、屋根下に天井が無いなど特定条件を満たす場合、梁の被覆を省ける緩和規定があります。ただし、“床面から梁下端まで 4 m以上”などの表現が曖昧で、検査機関ごとに解釈が割れることも。
- 背景
- 工場・倉庫で天井高が高い場合、被覆コストが数千万円単位で変わる。
- フラットバーや母屋を含むかなど、部材の境界条件が未整理。
- 推奨アクション
- 早期に建築主事/指定確認検査機関へ事前照会し、公式文書で回答を得る。
- 免除を採用する場合でも、防火区画や貫通部ディテールは大臣認定図に準拠させておく。
3. 海外製膨張型塗料の採用 ― 「ULがあれば足りる?」問題
欧米では UL、CE の認証を取得した耐火塗料が豊富ですが、日本の確認申請では国内大臣認定(FP 番号)が必須です。海外カタログ性能を鵜呑みにすると、申請直前に「認定がない」と頓挫します。
- 背景
- 日本は構造部の耐火を 仕様規定で担保する国際的にも特殊な制度。
- UL の試験炉は ISO 曲線、日本は JIS(旧 BS 準拠)で温度履歴が異なる。
- 推奨アクション
- 国内大臣認定(FP 番号)の付与状況を必ず確認
- 代理店を通じて **「構造方法等の個別認定」**を取得(試験 3〜6 か月、コスト数百万円)。
4. アスベスト含有既存被覆の改修 ― 「どこまで届出?」問題
改修現場で古い吹付けロックウールを撤去する際、大気汚染防止法の事前調査~届出範囲が複雑です。「部分補修なら届出不要」と誤解すると、行政指導や工期遅延リスク大。
- 背景
- 2022 年改正でレベル 2 建材(吹付けロックウール等)も事前調査・掲示板設置が義務化。
- 元請が届出を怠ると、罰則(指示・罰金)や元請企業名の公表リスクあり。
- 推奨アクション
- 着工前に専門調査機関の分析結果報告書を取得し、石綿含有有無を確定。
- レベル 2 の場合でも 隔離養生+負圧ブースを基本とし、近接テナントに説明。
- 既存梁の局所撤去後は、新旧被覆の界面処理(プライマー+繊維補強)を仕様書で指定。
5. 小梁の耐火被覆要否 ー 「主梁だけで良いの?」問題
- 背景
- 告示1399号は「柱・梁」に一括で厚さを示すのみで、大梁/小梁の区別を規定していません。
- 実務ではデッキプレートを支える L=2〜3 m 程度の小梁を「床版下部材」と位置づけ、主要構造部か否かの判断が分かれるケースが多々あります。
- 傾向
- 官庁・病院:公共建築工事標準仕様書に倣い 小梁も大梁と同等厚さで被覆する指示が一般的。
- 民間オフィス:デッキ一体設計+1 h耐火の場合、コスト圧縮で 小梁のみ塗装仕上げを提案されることがある。
- 傾向
- 推奨アクション
- 耐火構造要否を早期協議。
ここまで来た!ロボット吹付け最前線
ロボティクスが進む建築業界。耐火被覆の吹き付け作業もロボットが行う時代が来ています。
清水建設が発表した「Robo‑Spray II」は、手作業比 生産性2.5倍、1日150 ㎡を自動吹付け。タッチパネル操作で位置補正まで全自動です。
<半自動化した耐火被覆吹付ロボ「Robo-SprayII」が威力を発揮~ロボットの生産性が2.5倍にアップ!~>

大林組も自律走行型ロボを開発済みで、人手3→1への省人化が見えてきました。
<新型「耐火被覆吹付けロボット」を開発、建設現場へ適用拡大>
このように、これからの建築業界においては、若手のうちからロボティクス+BIM連携のQCフローを体験・知識として知っておくと、市場価値が爆上がりします。

コスト感&見積りのコツ
- 吹付けロックウール:5,000~8,000 円/㎡
- 耐火板:7,000~10,000 円/㎡(加工手間でブレ)
- 膨張型塗料:12,000~18,000 円/㎡(薄膜+美観で選ばれる)
⚠️ 上表は参考値です。人工や仮設・養生なども別途かかるので注意してください。
まとめ―若手エンジニアが明日すべき3つ
1.条文を味方に付ける
施行令107条と告示1399号は“暗記レベル”まで読み込み、耐火時間と厚さの根拠を即答できるように。
2.FP番号とグレーゾーンを制する
図面には必ず大臣認定(FP)番号を併記し、吹付け厚さや屋根梁免除など曖昧な部分は“協議記録+データ”で白黒を付ける。
3.DXで品質と生産性を底上げ
点群測定で厚さを可視化し、ロボット吹付けやBIM連携QCを体験。省人化とエビデンス強化で現場価値を高めよう。
🔥 耐火被覆は「塗る」から「設計し、証明し、DXで管理する」時代へ。
明日、あなたが手掛ける梁や柱が“火の試練”に耐え切れるように——この記事をあなたのロードマップにして、もっと安全で強い建物づくりに挑戦してください。現場でお会いしましょう!
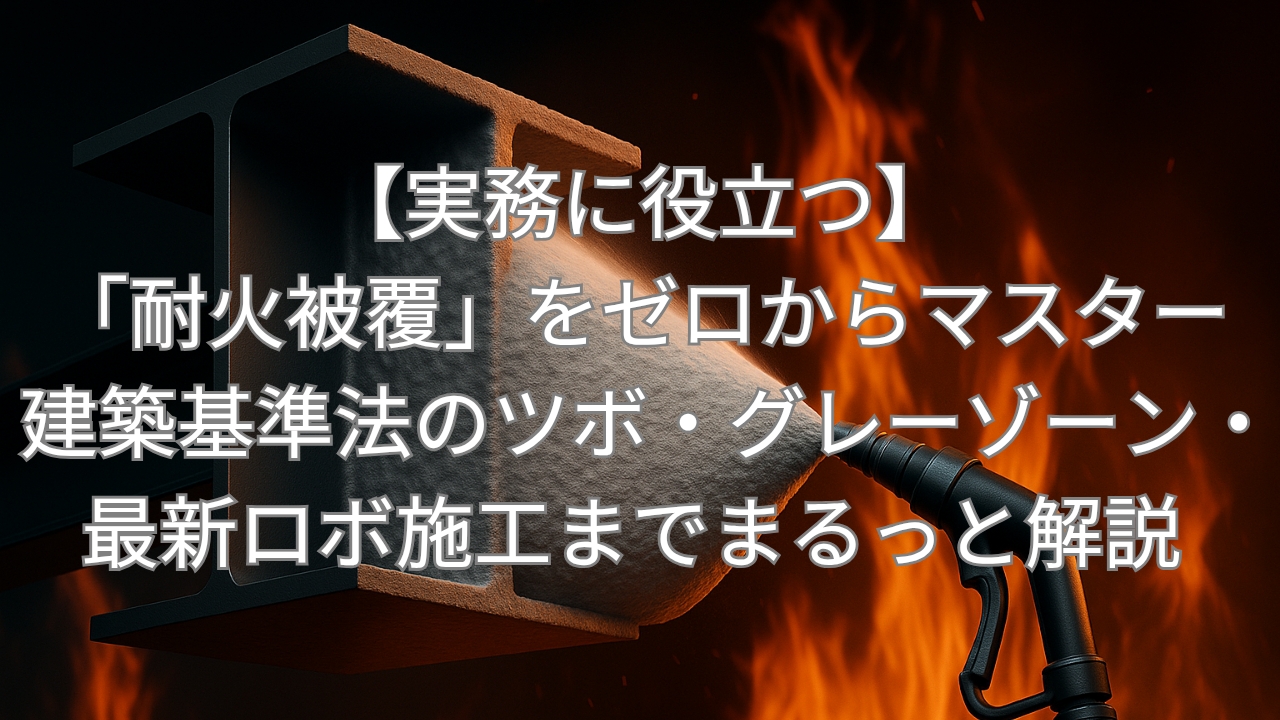
コメント